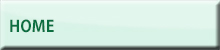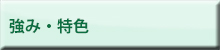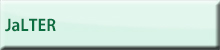内海域環境教育研究センターの強み・特色
内海域環境教育研究センタ-は、瀬戸内海などの閉鎖性海域の自然環境に関する基礎的研究と教育を行うほか、沿岸環境の保全と修復に関わる産官学連携研究を行うことを目的として設置され、「先端研究と文理融合研究で輝く卓越研究大学へ」をビジョンとして掲げる神戸大学における基幹研究推進組織の一つとして位置づけられている。
本センターは理学部附属臨海実験所(昭和38年設置)を母体とし、平成7年に学内共同利用の省令施設として設置された内海域機能研究センターを、神戸大学と神戸商船大学との統合を機に拡大改組したものである。令和2年度に「沿岸環境化学研究分野」、「沿岸環境解析研究分野」、「集水域生態系研究分野」、「海域生物多様性研究分野」の4つの研究分野に改組を行った。それぞれの専門分野から沿岸環境に関する研究を行うとともに、分野間で協働し、沿岸域の自然環境の保全や修復に資する教育研究を実施している。また、ナショナルバイオリソースプロジェクト「藻類」(中核機関:国立環境研)に「大型藻類」担当の分担機関として参加しており、「海藻類系統株保存室」を設置して、海藻類系統株保存事業の推進をはかっている。
臨海教育研究施設である「マリンサイト」は、平成31・令和元年度から令和5年度まで、教育関係共同利用拠点として認定継続をみとめられ、学内外の学部・大学院学生を対象に様々な教育プログラムを提供すると共に、周辺海域における研究活動の支援を行っている。
各研究分野の主な研究内容
海域生物多様性研究分野
内海域における水生生物の生物多様性と生態の解析,及びこれらの生物を指標として内海域環境を評価・モニターするための手法に関する基礎的研究を行う。集水域生態系研究分野
沿岸生態系に大きな影響を与える溜池,湖沼,河川,河口域などの集水域の生態系がもつ生物多様性と生態学的特性について,沿岸生態系との連環の解明を目指した基礎的研究を行う。沿岸環境化学研究分野
人間活動による沿岸環境への影響を評価するとともに,汚染された沿岸環境を修復し,管理することを目的とした研究を行う。沿岸環境解析研究分野
大気・海洋環境の変動によって内海域が受ける擾乱をモニタリングと実験により解析し,人間活動と調和した沿岸域の実現を目指した基礎的研究を行う。研究面での強み・特色
海域生物多様性研究分野では、センターの母体である臨海実験所時代から海藻類の基礎生物学的な研究や生物地理に関わる研究で優れた研究成果をあげてきており、藻類の系統分類や進化、生態の研究に特色がある。たとえば同分野教員らによるユーグレナの走光性光受容に関わる新規蛋白質複合体の構造と機能の解明(Nature, 2002)、紅藻類のクロロフィルdがシアノバクテリア由来であることを明らかにした研究(Science, 2004)、多細胞海藻類における初の全ゲノム解読・解析に成功した国際共同研究(Nature, 2010)などの科学的に重要な成果や、東日本大震災時の原子力発電所事故による海藻類の放射性物質汚染に関するモニタリング(J. Plant Res., 2014)や、大陸を越えて外来種となった海藻類の起源と拡散経路の推定に関する研究(Phycologia, 2006)など社会的に大きなインパクトをもつ研究成果をあげてきた。
集水域生態系研究分野では、森林の源頭域から河川を通じて、湖沼や海洋沿岸に至る流域を対象として、水生生物の進化・生態・生活史に関する基礎研究や生物多様性と生態系機能の関係を解明する学際研究など幅広く展開している。生物が関わる自然現象を分子レベルから生態系レベルまで階層横断的に理解することを通じて、集水域の人間活動が沿岸環境や生物多様性・生態系機能に及ぼす影響を評価し、保全・修復に資する科学的知見を社会と共有することを目指す。特に、マリンサイトが位置する大阪湾は、京阪神地区の社会・経済活動の影響を色濃く反映する。瀬戸内海で最大規模を誇る1,450万人の流域人口を抱える琵琶湖-淀川流域を対象として、現在、集水域の人間活動が生態系の栄養バランスや栄養循環機能に及ぼす影響を評価する手法の開発に取り組んでいる。安定同位体を用いた先端技術や社会協働などの超学際アプローチを導入するために、京都大学生態学研究センターや総合地球環境学研究所などの共同利用研究機関と連携するとともに、内海域が抱える環境問題を地球規模で解決するために、海外の研究機関と国際共同研究を推進している。
沿岸環境化学研究分野では、海域で意図的に使用される船底防汚剤などの有害化学物質について、生態毒性学の視点から生態影響と環境動態を把握し、生態リスクを評価してきた。 船底防汚剤Cybutryneとその分解産物が日本沿岸海水中に残留することを、カナダ国立水科学研究所との共同研究によって2003年に報告した。その後、本防汚剤を含めて種々の防汚剤(親化合物)と分解産物の生態影響をバッテリーバイオアッセイ(細菌、植物プランクトン、動物プランクトン、水生植物、ウニ、魚類など)を用いて評価し、生態リスク評価のための知見を集積してきた。2008年に国際条約によって有機スズ化合物の船底防汚剤としての使用が禁止されて以降、現在はCybutryneの使用が禁止されるべきかが検討されている。 この経験をもとに、現在は他研究機関との共同研究により、沿岸海水の表層マイクロ層に浮遊しているマイクロプラスチックを含む有害な粒子の残留実態と生態影響に関する知見の集積、海洋生分解性プラスチックの実海域における分解性に及ぼす因子解析などに取り組んでいる。 また、当センターの海藻類系統株保存室と海域生物多様性研究分野、バイオシグナル総合研究センターとの共同研究によって、海藻類を用いた新しい水環境管理手法の開発に取り組み、これが海事科学研究科のフラッグシップ研究の一部にもなっている。
沿岸環境解析研究分野では、海事科学研究科の練習船深江丸や小型舟艇などを用いたフィールド研究に加え、ラボ実験や数値実験など多様な研究手法により成果を挙げている。研究課題の一つは、沿岸域と相互作用する多様な海洋細菌の環境適応システムの解析である。国際条約が発効し、船舶バラスト水と堆積物が管理対象となっている。寄港地へ侵入する海洋細菌群集の定着を推定するため、バラスト水試料を対象に海洋細菌群集を計数し、堆積物の管理が多様性維持に重要と指摘した(Mar. Pollut. Bull., 2005)。国際条約が発効し、トリブチルスズの海洋での使用が禁止されているが、本化合物は堆積物中に残留しているといわれている。微生物群集に与える毒性について検討し、菌体表面にトリブチルスズを吸着する耐性菌が存在すると (Int. J. Mol. Sci., 2008)、近傍の細菌群集の生菌数が減少することを指摘した (Biocontrol Sci., 2017)。沿岸域で単離した耐塩性細菌の温度ストレスを伴う塩ストレス適応について検討し、37ºCでは、NaCl耐性は減少するが、KCl耐性は維持されることを明らかにした (Biocontrol Sci., 2020)。海洋中のK+濃度はNa+濃度の1/50程度で、数十億年大きな変化はないとされている。K+耐性菌の起源は大変興味深い。研究課題のもう一つは、気候変動や自然災害に対する沿岸域のレジリエンス強化である。瀬戸内海と四国南方沿岸で海水中温室効果ガス濃度の計測を20年近く継続し、瀬戸内海中央部は夏季に二酸化炭素の排出源になる可能性を示した(Springer, 2020)。平時の基礎生産環境として、富栄養化が著しい大阪湾(Mar. Pollut. Bull., 2008)やマニラ湾(La Mer, 2012)での実測に基づく数値生態系モデル解析を行い、赤潮発生原因を明らかにした。これに対し災害時の海洋環境として、津波が引き起こす環境擾乱を潮汐を考慮した津波モデル(Int. J. Offshore Polar Eng., 2016)と海底堆積物・物質の巻き上げ推定モデルにより予測し、大阪湾奥では津波後の水中重金属濃度が環境基準を大幅に上回り(Springer, 2019, 読売新聞、朝日新聞、2018)、約2カ月で定常状態になる可能性を示した(J. Water & Env. Tec., 2018)。沿岸域での温室効果ガス長期実測データや災害時の海洋環境予測は、世界でも類を見ない。
沿革
1954年(昭和29年)、神戸大学に理学部が設置されて以来、附属臨海実験所設立に必要な適地が県内に探し求められていた。1963年(昭和38年)に淡路島岩屋に淡路町から土地及び建物の寄付を受け、学内措置として臨海実験所が設立され、教育研究活動が開始された。 1966年(昭和41年)、教育実習施設として管制が布かれ、助教授1名、技官1名の定員が配置された。その後隣接地を購入し、1983年度(昭和58年度)に建物の全面的な増改築が行われた。 1987年(昭和62年)、助教授振替の教授、学内措置による助手の配置等があり、1995年(平成7年)4月、拡充改組により「神戸大学内海域機能教育研究センタ-」として新たに発足した。 2003年(平成15年)10月,神戸大学と神戸商船大学との統合に伴って,神戸商船大学の教官3名が加わり,「神戸大学内海域環境教育研究センタ-」として拡充改組した。 2007年(平成19年)4月,「神戸大学自然科学系先端融合研究環内海域環境教育研究センタ-」として改組した。 2014年7月,「教育関係共同利用拠点」に認定された。 2016年4月,大学の機構改革に伴い,基幹研究推進組織の一つとして「神戸大学内海域環境教育研究センター」に改称した。